Asu no chikyû sedai no tameni
(1975)–Willem Oltmans–Willem Oltmans, Asu no chikyû sedai no tameni. Japan Publications Inc., Tokyo 1975
DBNL-TEI 1
Wijze van coderen: standaard
-
gebruikt exemplaar
eigen exemplaar dbnl
algemene opmerkingen
Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Asu no chikyû sedai no tameni van Willem Oltmans uit 1975. Dit is de Japanse vertaling van het tweede deel van ‘Grenzen aan de groei’ uit 1974.
redactionele ingrepen
Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (16) is niet opgenomen in de lopende tekst.
[pagina 1]
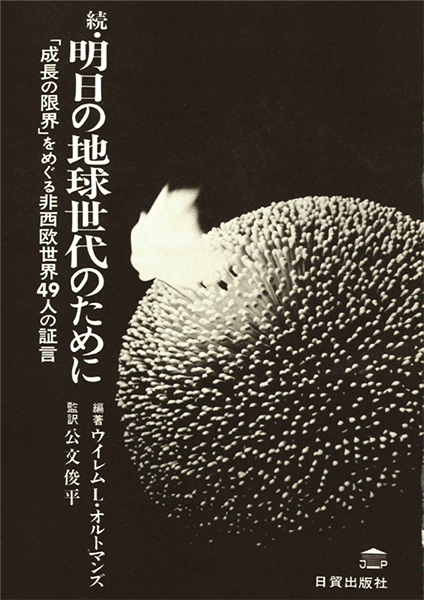
[pagina 2]
Grenzen aan de groei 2 Gesprekken over het rapport van de Club van Rome Willem L. Oltmans
Copyright © 1974 by A.W. Bruna & Zoon
Original Dutch language edition published by A.W. Bruna & Zoons Uitgeversmij B.V., Utrecht, Holland
Japanese translation and publication rights arranged with the author through Japan Publications, Inc., Tokyo
[pagina 9]
目次
| まえがき | アウレリオ・ベツチェイ |
| 第二卷への序言 | W・L・オルトマンズ |
| ローマ・クラプ | |
| 著者紹介 | |
| 1 インディラ・ガンジー | 17 |
| 2 モイセイ・S・マルコフ | 28 |
| 3 アプデルカデル・チャンデルリ | 34 |
| 4 島秀雄 | 45 |
| 5 P・S・サグデェーェフ | 51 |
| 6 ホーヘ・A・サバト | 63 |
| 7 ェマヌェル・アヤンカンミ・アヤンデレ | 71 |
| 8 鄧小平 | 79 |
| 9 ミハイル・スラトコフスキー | 89 |
| 10 アンドレイ・マルコフ | 89 |
| 11 アナトーリイ・マルーヒン | 89 |
| 12 チャクラウアルティ・V・ナラッムハン | 103 |
[pagina 10]
| 13 衛藤瀋吉 | 110 |
| 14 中根千枝 | 120 |
| 15 ルイス・ェチェべリア・アルバレス | 130 |
| 16 アミルヵル・ O ・へレラ | 137 |
| 17 レオボルド・ S ・センゴール | 145 |
| 18 アレックス・ N ・レオンティェフ | 150 |
| 19 佐藤方哉 | 166 |
| 20 南博 | 179 |
| 21 ビクター・ L ・ウルキティ | 193 |
| 22 茅陽ー | 209 |
| 23 青木昌彦 | 216 |
| 24 ラガバン・ N ・イイエル | 227 |
| 25 アレクサンドル・ェフレモフ | 236 |
| 26 ジョセフ・バィェストヵ | 248 |
| 27 アクリル・レンマ | 254 |
| 28 へリオ・ジヤグアリべ | 260 |
| 29 へルナン・サンタ・クルズ | 269 |
| 30 ジェルメン・ M ・グヴィシアニ | 277 |
| 31 大来佐武郎 | 288 |
| 32 リ・クアン・ユー | 299 |
| 33 モヒト・セン | 306 |
[pagina 11]
| 34 ゲオルギー・ A ・アルバトフ | 319 |
| 35 ワレンティン・ M ・べレジコフ | 332 |
| 36 アダム・シヤフ | 342 |
| 37 川喜田二郎 | 352 |
| 38 林 雄二郎 | 361 |
| 39 河野洋平 | 370 |
| 40 エシヤン・ナラギ | 377 |
| 41 野口武彦 | 389 |
| 42 ゾーヤ・ヤンコワ | 399 |
| 43 小松左京 | 409 |
| 44 ロメシ・タバール | 420 |
| 45 ティサ・ウィジェイエラトネ | 427 |
| 46 モハメド・カツサス | 438 |
| 47 マーティ・ェルマンテイラ | 449 |
| 48 アテケ・ H ・べルマ | 458 |
| 49 アウレリオ・べツチェイ | 471 |
| 監訳者あとがき | 485 |
| 翻訳者紹介 | 490 |
[pagina *1]
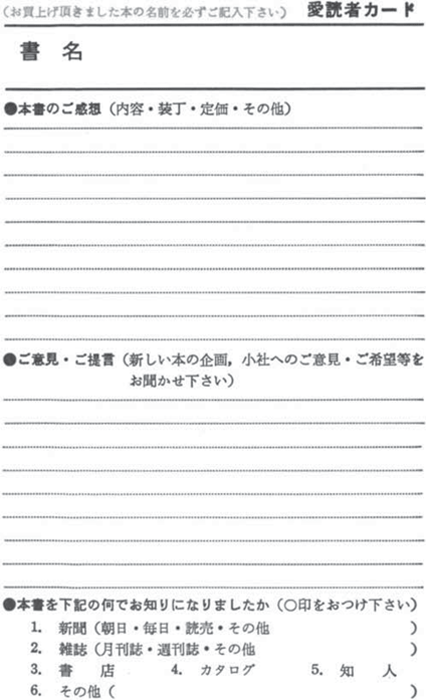
[pagina *2]
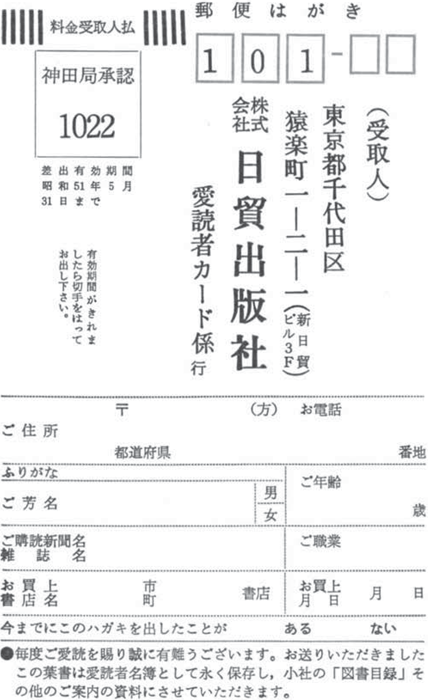
[pagina 490]
翻訳者紹介
東江 優(あがりえ まさる)
昭和10年生。
昭和36年琉球大学文理学部英語英文学科卒。
昭和39年インデイァナ大学教育学修士。
沖绳鼎立教育センタ一研究主事 (教育工学) 。
琉球大学非常勤講師。
論文:「視聽覚教育の実態に関する調查研究」他。
亀川正敬 (かめかわ まさゆき)
昭和18年生。
昭和37年琉球大学文理学部英文学科卒。
昭和39~43年,インド留学 (ラーマ・タリシユナ ミツションニヒンズ一教教団でインド哲学を研究) 。
昭和44~45年,ハワイ大学で英文学と哲学を研修。
興南高等学校教論。
沖繩大学,沖繩国際大学非常勤講師。
論文:「ヒンズ一教の哲学」,「理想社会を求めて」,他。
公文俊平 (くもん しゅんべい)
昭和10年生。
昭和32年東京大学経済学部卒。
昭和43年,インデイァ大学 Ph・D. (経済学) 。
東京大学教養学部助教授。
著書:『一般システムの諸類型』 (学習研究社情報银社会科学講座第6巻所収) ,『経济体制』 (共著,岩波書店) ,他。
訳書:『ソ連経済』(アレク・ノーグ著,日本評論社) ,『経済学を超えて』(ケネス・ボ一ルデイング著,竹内書店) ,他。
玉城政光 (たまき まさみつ)
昭和4年生。
昭和29年琉球大学語学部英文学科卒。
昭和33年,ジョージ・ビーボディ教育大学修士。
昭和47年,ニューョ - ク大学教育学博士。
琉球大学教育学部教授。
論文:「学習個別化に関する研究,(I)(II)」,‘A Study of the Concept of Mind,’ 他。
仲里一彦 (なかざと かずひこ)
昭和18年生。
昭和41年琉球大学文理学部英語英文学科卒。
昭和46年ウェスターンミツガン大学院教育学修士。
沖绳鼎立糸満高校教論。
沖绳国際大学非常勤講師。
中村哲雄 (なかむら てつお)
昭和14年生。
昭和37年琉球大学教育学部卒。
昭和43年アイオア大学教育学修士。
真嘉比小学校教論。
琉球大学、沖绳国際大学、沖绳女子短期大学、各非常勤講師歷任。
長尾史郎 (ながお しろう)
昭和16年生。
昭和44年一橋大学経済学部卒業。
昭和46年,カールトソ大学 (カナダ) M.A. (経済学)。
一橋大学大学院経済研究科博士課程在学。
訳書:『大転換』(カール・ボラニー,東洋経済新報社,共訳)。
論文:「システムと『主体』」,『新しい政治経済学を求めて第5集』(勁草書房)。
[pagina 491]
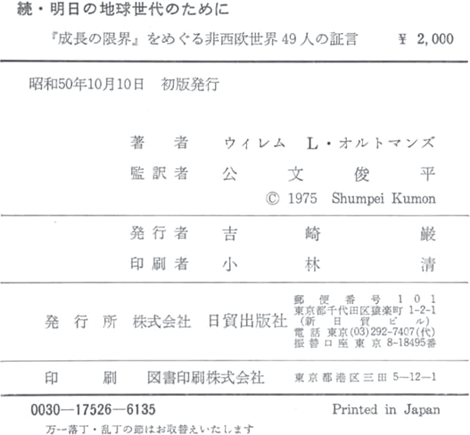
[pagina 492]

600ページをこえる本書を、しかも、同じパターンでくリかえされるインタビューの記錄を読み通すのはかなりの努力と集中力を必要とする。それら、一人一人の発言が、密度の高いものであるだけに、なおその感を深くする。一度ざっと読んでから、それぞれが関心を持つ分野に近い人たちの発言をじっくリ読みなおすという読み方もあるかもしれない。対談参加者一人一人の略歷や、特に重要著作の邦訳が紹介されているのは、一般読者、特に、これをもとにして、さらに問題を堀リ下げたいと頭う人々にはありがたい配慮である。
ー (昭日新間)
本書は『成長の限界』をめぐる世界知議人71人の見解を对談記錄の形で収錄したものであるが、誠にクイムリーな企圖であり、数多くの有益な示唆を与えてくれるものである。登場する人物のなかには、J・ハックスレー、レヴイニストロース、D.ガボール、G.ミュルダール、P.サミュエルソン、M.ミードなど『成長の限界』についてコメントを是非一度は聞いておさたいと思うような世界の頭腦がずらりと並んでいる。心情的で軽傅な終末論やその裹返しの楽觀論のムードをいたすらにもてあそふまえに、冷靜かつ強勸な思索のために、本書 を是非熟読されんことを広く一般読者にすすめたいと思う
ー (サンケイ新聞)
昨今の終末思想の基礎にはこのMITレポートのもつ危機意議との関連を見逃がすことがでさないが、本書序文で大来佐武郎氏が述ベているように、経済成長を単にネガティブな觀点からだけ論するのではなしに、「持続可能な成長」を実現するという積極性が求められる。その意味で本書は一つの手がかりを与えてくれる。なお71人の対談者の個性がよく訳出されており、卷末に邦訳された参考文献も研究資料の手引きともなる
ー (每日新聞)
大冊ではあるがインタビューという形で読みやすいものだから、是非一読を勧めたい。それにつけても感心するのは、この編者オルトマンズがまことによく準備をした上でこの対を連んでいることである。相手の諸論者における見解をじゅうふん押えて適切な間いをしているばかりでなく、それに他からの批評もからめて相手からの返答を剌戟する手口など心にくいほどである。「まえがさ」によれば、編者はさらに社会主義国および第三世界の人々へのインタビユーによる第二集を作成中とのことである。おそらくこれもまた興味深いも のになることであろう
ー (公明新聞)

